2009年 10月25日(日)
哲学の秋
10月17日朝日カルチャーセンター新宿で、西研さんとのジョイント講座、ヘーゲル「法哲学」の後期授業が始まった。
初日はまず講師二人の「マイブーム」(この言葉、まだ生きてますか?)のお話。
竹田さんの最近の「趣味」は、「哲学完全解読」、直近ではカントの『純粋理性批判』の刊行が予定されており、毎朝早起きして取り組んでいるそうです。竹田さんは、(有名な「カラオケ」をはじめ、テニスやオーディオなど)多彩な特技や趣味をもった人なのだが(10年ほど前までは、ファミコンにも相当はまっていたそうです)、いまは諸々の欲望が「哲学」に収斂しているとの話。イチローの「野球」、石川遼の「ゴルフ」、のような感じですね。好きこそ物の上手なれの世界水準。
西さんも、ほぼ同様に「哲学」に浸る毎日だそうです。二人の共著となる『ポケット版・ヘーゲル精神現象学』が、来春の刊行をめざして、着々と進行中。一昨年デビューした『完全解読・ヘーゲル精神現象学』(講談社メチエ)が、かなり本格的な内容だったので、今回はさらに噛み砕いて「ほんとうに寝ながら読めるヘーゲル」にしたいな(竹田さんのコメント)、ということです。西さん自身の単著としても、社会学者で現象学研究会のメンバー、菅野仁さんとの対談本がもうじき刊行の予定。さらに『哲学のモノサシ』(NHK出版)に続く「哲学絵本」も進行中で、これからの西さんの哲学の展開を伝えてくれる内容になる、というお話でした。楽しみです。
その他、西さんは勤め先の和光大学で、「ジャズ」の講義もしているそうです。これも「趣味」かな―、とのことです。そういえば、マイルス・デイビスの自伝はとても面白いよ、という話をごく最近西さんがしていた。どんな講座なんだろう。きいてみたい。もし、受講した方で奇跡的にこれを読んでおられる方がいらっしゃったら、ちょこっと教えてもらえませんか。
いま、社会のさまざまな現場で(職場にしろ私的な場面にしろ)、それぞれの居場所から現状をよく見つめ、問題を共有化しあい、「この先」を見渡していくことを可能にする思考方法の確立が、希求されていると思います。「哲学」を、その「思考の原理」として再構築することの意義もそれだけ大きい。で、竹田さん、西さんはそうした仕事を(「趣味」と言っていいほど)「楽しみながら」「集中して」展開している様子。「哲学完全解読」は(そのための労は傍目からみるとすごいものなのですが)、いってみれば「わかる喜びを共有する(その思想の本質的なよさを広く共有しあう)」ものですし、それを考えると「楽しい」仕事なのかもしれません。
初日の「法哲学講座」は、ヘーゲル哲学の今日的価値の解説。ヘーゲル哲学の最大の意義は、人間の欲望の本質を「自己価値への欲望」「承認欲求」として(的確に)とらえ、その展開のもと社会や倫理のありようを見取ろうとしたこと。そして、近代(社会)の本質を、誰もがそうした生の与件(自己価値への欲望)に即して生きられるという「自由」の展開において描き出したことにある。さらに、ヘーゲルは、その近代が必定生み出す、「幸福への自由競争」による社会格差の問題、「善の自由競争」による思想対立の問題を視野に入れ、(「事そのもの」「良心」という概念において)その解決への方向性を示した。「批判」のみに終始する、現代思想の「反哲学的」言説とは一線を画する、本質的な思想への志が息づいている。「自由」であることは、同時にとても孤独なことでもある。多くの人々が今、抱え込んでいる「寄る辺ない苦しみ」をくみ上げていく視点がヘーゲル哲学に内包されている……そんなことを竹田さん・西さんのお話を通して再確認させてもらう(間違っていたすみません)。難解なテクストにまたチャレンジしていくモチーフをいただいた感じです。
西さんによると、後期講座で購読する、「法哲学」の後半部分(家族・市民社会・国家)については、ヘーゲル思想のエッセンスに基づきつつ、「リニューアル」する必要がある、とのことです。それ、どんなことなんだろう。ますます楽しみになってしまいました。
だって,ここが「メッカ」ですから。
10月5日(月)、町田NHK文化センターで、フッサール「現象学の理念」購読講座がはじまった。町田講座で、竹田さんの本格的哲学購読講座が開かれるのはこれがはじめて。「人が集まるのかしら……」という懸念があったそうだが、いざふたを開ければほぼ満席状態。しかも「竹田さんの講座は今回がはじめて」という方もたくさん参加された。
でも、小田急線町田界隈は竹田さんと西さんの住まいのほど近く。いってみれば現象学のメッカです。やはり界隈に住み学生時代バイトをしていたこともありこの地に愛着を持つところの(カントのドイツ語並に長い冠飾句だ……)管理人としては、講座の盛況、何にも不思議はないはず、だと思います。
初日の講座は、フッサール現象学の本質的な価値について。「反哲学(反形而上学)」の潮流のなか、現象学は絶対的、客観的な真理を基礎付けようとする(古い)「哲学」の典型として誤解を受けてきた。しかし、その真意は、むしろ、絶対的客観、絶対的真理という前提を禁じ手にしたうえで、「普遍的」な認識を、「共通了解」によってとらえだす思考の原理の確立をめざしたことにある。(この思考方法の現実的問題に対する射程は大きい。)……ということを、パワーポイントを駆使して解説してくださった。竹田さんの図説はとてもわかりやすくかつ、ユーモアがあり(漫画家の藤野美奈子さんも、その画力を高く評価している)、パワーポイントはとても効果的なツールとなっています。
講座の後は、近くの居酒屋で懇親会。新しい方との出会いもあり、「HP見てますよ」「でも更新とまってますね」などとお声がけいただいたりもして、たいへん幸せな時間をすごさせていただく。懇親会の場も含めご配慮いただいた、講座ご担当の榎本さん、毎回ありがとうございます。
ドイツ語研、いよいよフッサールへと……
10月6日は研究室でドイツ語研。長らく購読したカント「純粋理性批判」もこの日が最終日。あまりに構文が難解で、文法的に???ということがあり、苦労させられたが、竹田さんのテキストに向き合う入念で真摯な姿勢に触れられたことは収穫かも。文意はとれても、構文的にきちんと腑に落ちないと先に進まない、という感じのこだわりです。そして、この購読の間も、「(完全解読の原稿の)ここは少しなおさくちゃ」と、チェックを重ねていた。『完全解読・純粋理性』。程なく形になるはずです。
次回からは、フッサールの『現象学の理念』にチャレンジ。がんばりたいと思います。
2009 年 9月13日(日)
新刊ゾクゾクと……
9月10日、社会学者橋爪大三郎さんとの対談本『低炭素革命と地球の未来』(ポット出版) が刊行された。地球規模でのエネルギー問題をどうとらえ、どのように処していくか、という大きなテーマの本である。竹田さんは、現実の諸条件を踏まえつつ、「より多くの人がよりよく生きられる一般的条件の維持と向上」という揺るぎない視点のもとから、未来への可能性を見出そうとしている。資本主義経済が、「自由の相互承認」という近(現)代社会の原理を展開していくうえでどのような役割を果たしてきたのか、今後に向けてどのような課題を提示しているのか、という(3月に刊行された『人間の未来』 が刊行された。地球規模でのエネルギー問題をどうとらえ、どのように処していくか、という大きなテーマの本である。竹田さんは、現実の諸条件を踏まえつつ、「より多くの人がよりよく生きられる一般的条件の維持と向上」という揺るぎない視点のもとから、未来への可能性を見出そうとしている。資本主義経済が、「自由の相互承認」という近(現)代社会の原理を展開していくうえでどのような役割を果たしてきたのか、今後に向けてどのような課題を提示しているのか、という(3月に刊行された『人間の未来』 で展開された)ことなども、明快に記されている。アクチャルな問題を、ちゃんと腑に落ちるように考えるためには、「哲学的思考」って欠かせないんだな……と実感させられます。ぜひ、ご一読くださいね。 で展開された)ことなども、明快に記されている。アクチャルな問題を、ちゃんと腑に落ちるように考えるためには、「哲学的思考」って欠かせないんだな……と実感させられます。ぜひ、ご一読くださいね。
これに先立ち、8月21日には監修をされた『面白くてよく分かる!フロイト精神分析』(アスペクト) が刊行。7月の『中学生からの哲学「超」入門』(ちくまプリマー新書) が刊行。7月の『中学生からの哲学「超」入門』(ちくまプリマー新書) から数えると……、1月1冊のペースで新刊が出ている。日々の研究や、綿密に準備をして臨まれているさまざまな講座が、こうした「アウトプット」に直結している感じだ。 から数えると……、1月1冊のペースで新刊が出ている。日々の研究や、綿密に準備をして臨まれているさまざまな講座が、こうした「アウトプット」に直結している感じだ。
研究室の灯は消えず……
で、夏休みも集中して勉強する竹田さん。8月14日、世間的に盆休みの時期に、研究室では「ドイツ語研」が開かれた。カント『純粋理性批判』の第3アンチノミーと「格闘」。でも、ドイツ語に堪能な西研さんが参加するようになって、読後の「スキッと感」が倍増した感じだ。西さんは、文法にも照らし合わせ、痒いところに手が届くような解説をしてくれる。とてもとても充実した時間になっています。
聞くところによると、竹田さんはこの盆休み期間、みずから研究室に缶詰になって(?なんか変な日本語ですね)フッサール『現象学の理念』完全解読の英訳に取り組まれていたそうだ。(英語の勉強にもなるので、とおっしゃる。頭が下がります……)現象学の本質を、広く世界へと発信していくというプラン、実現はそう遠くなさそうだ。
『純粋理性批判』の完全解読本、朝カルの講座がベースとなった『精神現象学・ポケット版完全解読』のプランも着々と進行しているご様子。今後もゾクゾクと竹田さんの本が楽しめると思います。
『経験と判断』、まだ5合目です……
9月5日は「現象学研究会」 。フッサール『経験と判断』の購読第2回目である。「第一篇 前述語的(受容的)経験 (第三章)」「第二編 述語思考と悟性対象」を読む。 。フッサール『経験と判断』の購読第2回目である。「第一篇 前述語的(受容的)経験 (第三章)」「第二編 述語思考と悟性対象」を読む。
「論理学」の本質を(「このわたし」という主観をモデルとした)世界の受け止め方、とらえ方という様相に立ち返り、つかみ取ってこう、というモチーフに共感しつつ、読み進めようとするのだが、とくにここのあたりの分析・記述が、それはもう細かく。かつ、(明晰な判断のよりどころとして)「客観的事物の知覚」をまずもっての起点にしていること、(だれにとってもそうみえるはずだという確信のもとにある)「客観世界」を「根源的時間」なるものとの関係のもとにとらえようとする記述など、「ちょっと違和感」のところも。ものごとをそのように対象化したり、共通の価値として(客観的なものとして)何かを見出そうとしたりする「欲望」の展開に照射したほうが、ずっとすっきりするのに……と思えてならない。
「これ、『論理学』から「巻き戻し」て、経験や判断をとらえようとしているのかも?」という感想なども出される。だが、「こうして『(事物)知覚』にこだわるのは、『論理学』の確かなよりどころを見出そうとする動機があるからではないか」という意見も。なるほど、と納得。しかし、「そもそも、なぜ『論理学』の根拠を問おうとするのか、ということ自体を明確にしておく必要があるんじゃないのかな……」という、石川テルキチ氏 からの(その後の「飲み会」での)意見にも、また深く納得。 からの(その後の「飲み会」での)意見にも、また深く納得。
険しい道のり、まだまだ5合目という感じですが、竹田さん、西さんの的確な読みや、メンバーとの語り合いに励まされつつ、なんとか上りきり、ちゃんと報告できるようにしたいな、と思います。 /管理人
2009年 8月2日(日)
これが終わると、夏休み
毎年8月最初の週末に開かれる朝日カルチャーセンター(新宿)の合宿講座は、竹田さんにとって「これが終わるとようやく一段落(夏休み)」という感じになるそうだ。それだけ気合を入れて取り組んでおられる。
8月1日から2日にかけて、その講座が開かれた。
題材はヘーゲルの『法の哲学』。「道徳」の章を中心に購読を進めた。
竹田さん・西さんの解釈は、(毎回のことではあるが)主張のポイントを明快かつシンプルに取り出すだけでなく、「なぜこの話題がここで取り上げられているのか」という詳細なレベルに至るまで疑問を氷解してくれる、「凄み」のあるものだった。『法の哲学』は「完全解読本」刊行のプランも進んでおり、竹田さんはこの間「けっこう大変だよ……」といいながら、集中して完全解読レジュメ作成に取り組まれていた。
それでも竹田さんは、ご自身でも腑に落ちていないことがあれば、講座の場で実直に告げる。西さんがその点に関してご自身の考えを出される。西さんとの対話を通して、解釈の輪郭がよりはっきりしてくる。受講生の質問からも、考察を深めていく糸口を見つけ出されているようだ。(一受講生として)充実した楽しい講座であるだけでなく、そういう竹田さんの真剣勝負の場に立ち会っているという昂揚感もわいてくる。
合宿恒例・夜のフリー質問会では、竹田さんの現象学の位置づけと評価をたずねる(なかなか)スリリングな内容のものがあった。これについては、西さんが「現象学(者)」をめぐる現況を瞬時のうちに素描してくださった。そのうえで(確信成立の条件をとらえ、たずねあうという)「現象学」の可能性を明快にとらえだしたのは、竹田さんならではのことで、今後その射程は大きい……と整理してくださった。西さんの「ミニ竹田青嗣論」。思わぬごちそうという感じでした。質問してくださった方、ありがとうございます。
また、7月30日に東工大で開かれた、橋爪大三郎さんとのジョイント講座「地球の危機と市民の行動」の内容も、竹田さんご自身が報告してくださった。(仕事の都合で出席できなかったので)ありがたかったです。
二日間とことん考え、語り合った本当に充実した合宿でした。
細かな配慮で支えてくれた担当の石井さん、どうもありがとうございました。
うなぎの「現象学」?
知力体力を振り絞った合宿の後、近くにあるおいしいうなぎ屋さんでスタミナをつける竹田さん。ご一緒させていただく。
席上、それぞれおすすめのうなぎ屋さんが話題になる。名古屋在住のみなっち(藤野美奈子)さんは、名物「ひつまぶし」について語る。
「『ひつまぶし』って、同じ一匹のうなぎでも、ごはんたくさん食べられていいですよね」と、アホな管理人。
「それ、どういうこと? うなぎって一匹から何人分もつくるわけだから、関係ないでしょう」と竹田さんに問いただされる。
そういえばそうかも。でも……
「注文を受けて、裂くところから始めるうなぎ屋さんもあるんですよね(行ったことないけど)。だから、基本は一匹一人前じゃないのかな。」
「なるほど、それもそうだね……。そういえば、いまみんなが食べてるうな丼、それぞれ尻尾が入っているよね。考えるに値するテーマかも。」
「でも、うなぎって、これよりずっと長いですよ。一匹で一人前とは思えないな。」と助手のM岡氏。
「焼くと縮むのかな。 うなぎの減少学?」と竹田さん。
……何が言いたいのかといいますと
①竹田さんは普段から腑に落ちない発言は見逃さない。だが、その発言の背景に一定の根拠と動機を認めれば、きちんと受け止める人である。
②竹田さんは駄洒落を愛する人である。その傑作は枚挙に暇がない。
以上でした。
/管理人
2009年 6月28日(日)
ご無沙汰してすみません……
管理人日記、ながらく更新できずにすみませんでした。冬眠を通り越し春がすぎてもまだ起きられず……という感じでしたが、一念発起して再開いたします、ので、よろしくお願いいたします。
「世界への第一歩」、まずノルウェーから
管理人が眠りに堕ちている間も、(当然)竹田さんは大活躍。この6月は、西研さんをはじめ、現象学研究会メンバーのI岡さん、I甲さん、T野さんとともに、ノルウェーで開かれた、現象学をテーマとした国際的な学会に参加。竹田さんは、「確信成立の条件を探る」という現象学の発想の核心について、西さんは、現象学のエッセンスをどうとらえ、社会への考察にどうつなげていくかということ、ほかの方たちも「救急医療」(I岡さん)、「カウンセリング」(I甲さん)、「教育(学)」(T野さん)という、各専門分野から、現象学に基づいた原理の構築や実践の可能性について発表なさったそうです。
医療や看護で、(この人に対して、どうすればよりよい医療を行うことができるか、というような)実証科学だけでは太刀打ちできない問題に日々直面する方たちが、人間的価値の問題を考察する手がかりを求め、現象学に関心を寄せていることは、国を超えて共通している様子。 でも、その現象学の発想の「キモ」が、(フッサールの超煩雑難解な言い回しのせいか)うまく理解されていない……ということも国を超えて共通した事態のようです。
一人ひとりの実存に寄り添いながら、ものごとの普遍的な価値を見出していくための思考の原理を掘り起こした、竹田さん・西さんの現象学解釈は、(きちんと伝えることさえできれば)きっと今後多くの方たちに(それぞれの現実に根ざした)可能性をひらいていくことになると思う。
ちなみに竹田さんは、今回の学会で「フッサール完全解読」のプランを伝え、多くの人が興味を示したそうです。「世界が完全解読をまっている」のだと、わたしは思います。(それにしても英語の勉強がこわいほど生きていますね。)
で、フッサールを読む。
6月27日は現象学研究会。冬眠春眠からさめ(?)た管理人は半年振りの参加(だが、(この間活動報告 をしてくれた小井沼氏に感謝です)。 をしてくれた小井沼氏に感謝です)。
課題図書はフッサールの『経験と判断』。竹田さんにいわせると、これは「難解がゆえに乗り越えること自体に快感がある山」のような本でだそうです。もちろんご自身は何度も乗り越えた山で、今回は、若いメンバーたちと一緒にもう一度道筋を確かめなおしてみる、という感じなのだと思う。ちなみに管理人は、何度か途中下山して今日にいたっています。
本の要諦は、「論理学」の本質を現象学的にとらえなおすこと。『緒論』では、(言語の)論理形式(による判断)のもとになっている、「ものごとのうけとめかた・とらえかたの様相」を、「知覚」という最もコアだと思える場面からまず見取っていこう、というような方法論が示され、なかなか興味をそそられる。ミスリーディングな術語である「超越論的主観性」についても、(決して真理が生成する特別な場というようなことでなく)もともとの客観を一切前提にせず、(だれにとってもそうであるはずだ、という客観的世界への信憑をナシにしたうえで)「わたし」にとってという場面からものごとのありよう、意味や価値が形づくられてきた(沈殿の)をとらえなおしていこう、という目的・方法に即してのものだということがけっこうわかりやすく語られていて、共感を受ける。
ただし、その後の「知覚」の分析が、それはもう執拗に細かく細かく……やはり先の道はけわしそうです。(ちなみに、こうして「知覚」から出発して、際限なく顕微鏡の確度を上げていくより、欲望相関的な世界構成という場からストレートにとらえていったほうがいいんじゃないかな……という竹田さんの意見もありました。)
以降2回に分けて「登山」の予定です。がんばって上りきり、フッサールの意図(なんでこんなふうに「論理学」の本質にこだわったのかということ自体を含めて)を見渡せたらいいな、と思っています。
/管理人
|
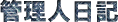 (2009年)
(2009年)